FJcloud実践
iperf3でFJcloud-Vのネットワーク性能を検証
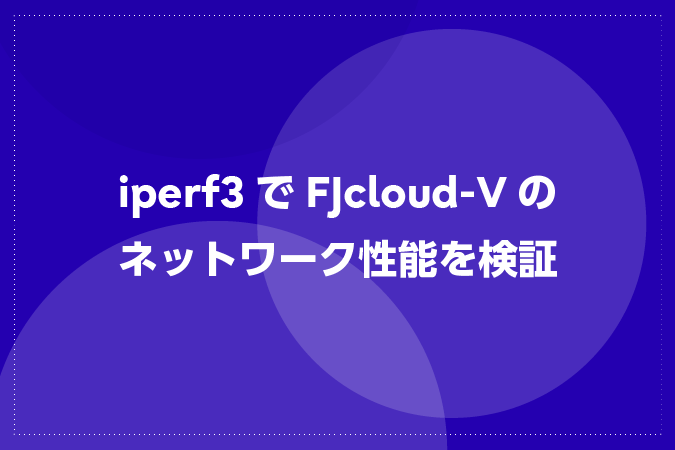
この記事は、ニフクラブログで2016-02-10に公開された記事を移転したものです。
クラウドサービスを利用する時に、ネットワーク速度がどれぐらいなのかは気になるところです。
そこで今回は私の会社のオフィス(東京・渋谷)から各リージョンへの上り下りのネットワーク速度、さらに各リージョン間のネットワーク速度を計測してみました。各リージョンは、東日本(east-1, east-2)、西日本(west-1)、北米(us-east-1)となっています。
注:本計測は、あくまで筆者の環境を使った計測時点での値であり、計測環境・計測時間によって異なる場合あります。参考程度に留めておいてください。
計測環境
計測に使用したのはネットワーク性能を計測するオープンソースのツール「iperf3」です。
Linux版が用意されているので、Linuxのサーバーを各リージョンにインストールして、計測を行いました。 手元側ではファイアーウォールなどの性能に制約されないよう、グローバルIPアドレスに直付けされた物理サーバーを用意して計測を行っています。
ただし、回線の都合上、オフィスからFJcloud-V(旧ニフクラ)への帯域は200Mbpsに制限されているため、上り帯域の上限は200Mbpsとなります。
計測結果
以下の表が、計測してみた結果です。
オフィスとリージョン間の結果
| 対象リージョン | アップロード帯域(オフィス→NC) | ダウンロード帯域(NC→オフィス) | アップロードレスポンス(オフィス→NC) | ダウンロードレスポンス(NC→オフィス) |
|---|---|---|---|---|
| east-1 | 205.0Mbps | 338.0Mbps | 4.5ms | 4.4ms |
| east-2 | 204.0Mbps | 338.0Mbps | 1.3ms | 1.5ms |
| west-1 | 189.0Mbps | 94.8Mbps | 10.5ms | 10.6ms |
| us-east-1 | 43.4Mbps | 14.6Mbps | 150.0ms | 150.0ms |
リージョン間の結果
| リージョンA | リージョンB | 帯域 A→B | レスポンス A→B | 帯域 B→A | レスポンス B→A |
|---|---|---|---|---|---|
| east-1 | east-2 | 600.0Mbps | 5.3ms | 227.0Mbps | 5.2ms |
| east-1 | west-1 | 434.0Mbps | 12.7ms | 65.6Mbps | 12.7ms |
| east-1 | us-east-1 | 68.5Mbps | 176.0ms | 53.8Mbps | 166.0ms |
| east-2 | west-1 | 905.0Mbps | 11.3ms | 949.0Mbps | 11.3ms |
| east-2 | us-east-1 | 66.4Mbps | 151.0ms | 63.6Mbps | 152.0ms |
| west-1 | us-east-1 | 77.5Mbps | 160.0ms | 69.8Mbps | 160.0ms |
結果を分析してみましょう。
東日本リージョンの結果分析
前述したとおり、アップロードは帯域制限がかかっているため、上限の200Mbpsにぶつかってしまっていますが、ダウンロードはeast-1リージョンに比べてeast-2リージョンの方が高速です。pingを使ったレスポンスタイムもeast-2リージョンの方が高速になっています。
理由としては、east-2リージョンの方がまだ利用率が低いこと、上流の接続が近いことなどが考えられます。いずれにしろ、東日本のどちらのリージョンも実用上は十二分な速度が確保されていると考えてもよいでしょう。
西日本リージョンの結果分析
オフィスからwest-1リージョンへの接続は、アップロードは189Mbps、ダウンロードは94.8Mbpsとなりました。
west-1リージョンから関東へのダウンロード速度が遅くなるのは、後述するリージョン間でもwest-1リージョン→east-1リージョンで発生しています。
ただし、west-1→east-2リージョンは高速なので、帯域制御などが行われているのでしょうか。レスポンスタイムは10msとなりますが、viエディタなどでテキストをスクロールさせてもストレスは感じません。西日本の拠点からの性能を測定できれば、もっと快適になるのではないかと想像しています。
北米リージョンの結果分析
オフィスから北米リージョンへの接続は、どうしても帯域速度は低下してしまうので、大きめのデータなどをアップロードしたい時には注意が必要かもしれません。レスポンスタイムは150msとなっていますが、間にWANアクセラレーターでも入っているのでしょうか、細かいコマンド入力などはやや引っかかりがあったりしますが、テキストスクロールのようにまとめて処理するものは意外にもスムースです。
リージョン間接続の結果分析
次にリージョン間の速度を見てみましょう。
傾向として顕著なのは、east-1リージョンからその他のリージョンへの下り帯域に比べて、その他のリージョンからeast-1リージョンへの上り帯域は性能が低くなっていることです。
一方、east-2リージョンとwest-1リージョン間は帯域劣化もなくかなり高速なので、もし東西でDR的な構成を取りたいのであれば、このリージョン間で構成するのが今のところはお勧めということになるでしょうか。
ネットワーク性能で見ると、east-2リージョンがなかなか優秀なようです。皆さんのリージョン選択の参考になれば幸いです。
